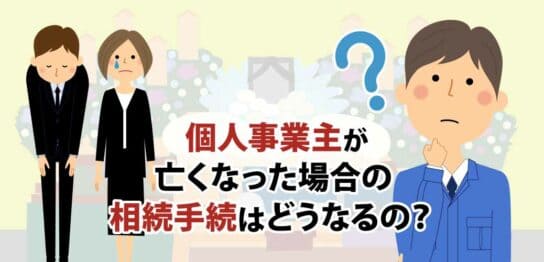- 死因贈与とは?
- 死因贈与と遺贈の違いとは?
- 死因贈与と遺贈のどちらを選ぶべき?
【Cross Talk 】死因贈与とはどのようなものなのでしょうか?
家族に遺産を渡したい場合、死因贈与という方法があることを知りました。死因贈与とはどのようなものなのでしょうか?
死因贈与とは、贈与者が亡くなった際に効力が発生する契約のことです。
死因贈与について詳しく教えてください。
あなたが亡くなった際に家族に遺産を渡すためには、いくつかの方法があります。この記事では、死因贈与という方法について解説していきます。死因贈与によく似た方法に遺贈という制度も存在しています。以下では、死因贈与のメリットやデメリット、死因贈与をすべき場合・遺贈をすべき場合などについて、弁護士が解説していきます。
死因贈与とは?

- 死因贈与とは?
- 死因贈与の成立条件とは?
死因贈与とはどのようなものなのでしょうか?
ここでは、死因贈与の意味やその成立条件について解説していきます。
死因贈与が成立する条件
死因贈与(しいんぞうよ)は、民法上の贈与契約の一種で、「贈与者が死亡した際に、あらかじめ指定した財産を受贈者に引き渡す」という内容の契約です。この契約は、財産を無償で他者に渡す点で通常の贈与と同じですが、効力が発生するタイミングが「贈与者の死亡後」という点で特異なものとなっています。 死因贈与は、生前贈与や遺贈と並んで、個人の財産を他者に引き継がせるための手段の一つです。それぞれの手法は異なる特徴を持ちます。
死因贈与の活用される事例として、親が「自分が亡くなったら自宅を子どもに譲る」という契約を結ぶ場合があります。また、「負担付死因贈与」という形で、贈与を受ける代わりに特定の義務を負うことを条件とする場合もあります。たとえば、「介護をする代わりに財産を譲る」といった内容が考えられます。
死因贈与と遺贈の違い

- 死因贈与と遺贈の違いとは?
死因贈与と遺贈とは、どこが違うのでしょうか?
いずれも家族に財産を譲るための方法ですが、ここでは死因贈与と遺贈の違いについて詳しく解説していきます。
| 死因贈与 | 不動産取得税が課されます(法定相続人でも4%)。 |
| 遺贈 | 法定相続人が受け取る場合は非課税ですが、法定相続人以外には4%課税されます。 |
| 死因贈与 | 一律2%課税されます。 |
| 遺贈 | 法定相続人は0.4%、法定相続人以外は2%が課税されます。 |
死因贈与のメリットとデメリット

- 死因贈与のメリットとは?
- 死因贈与のデメリットとは?
家族に遺産を渡したい場合、死因贈与を選択すべきなのでしょうか?
死因贈与には、メリットとデメリットがあるため、それらを考慮したうえで判断することが重要となります。
死因贈与のメリット
死因贈与のメリットとしては、以下のものが挙げられます。遺贈に比べて手続きが簡単
死因贈与は遺贈のように遺言書の厳格な形式が必要ありません。死亡後の検認手続きが不要で、手続き的なハードルが低いと言えます。無効とされるリスクが低い
書面の不備があった場合でも、契約自体が無効になる可能性は低いといえます。 遺贈の場合、法律で細かく定められた形式を守らないと無効になる可能性がありますが、死因贈与はこの点で柔軟であるといえます。渡したい相手に確実に財産を渡せる
贈与者と受贈者の合意に基づく契約であるため、受贈者が確実に財産を受け取れることが保証されます。 合意書を作成しておくことで、他の相続人とのトラブルも回避できる可能性が高いでしょう。負担付死因贈与による安心感がある
負担付死因贈与では、「特定の義務(例: 介護)を履行する代わりに財産を贈与する」という内容が含まれるため、贈与者・受贈者双方に安心感があります。亡くなった方の財産を承継するのに正当な理由があることを他の親族も理解しやすいでしょう。受贈者が事前に財産内容を把握できる:
死因贈与は契約時点で財産の内容が明示されるため、受贈者はどんな財産を受け取るかを事前に知ることができます。これにより、税金や資金の準備を前もって進めることが可能です。死因贈与のデメリット
上記に対して、死因贈与のデメリットには、以下のようなものがあります。相手の同意が必要
死因贈与は契約であるため、受贈者の同意が必要です。一方的な意思表示で成立する遺贈に比べて、受遺者と契約の内容を共有し、合意をする必要があります。契約書がないとトラブルに繋がる可能性がある
契約書を作成していない場合、他の相続人との間で争いが発生する可能性が高いです。証拠を残すためにも、必ず契約書を作成し、公正証書にするのが望ましいでしょう。贈与の内容を秘密にできない
死因贈与は受贈者に財産内容を明確に伝える必要があるため、遺贈のように贈与内容を秘密にすることができません。そのため、生前にしっかりと当事者間で話し合いを行っておく必要があります。不動産にかかる税負担が大きい
死因贈与で不動産を取得する場合、不動産取得税(4%)や登録免許税(2%)が課税されます。 遺贈では法定相続人に対してこれらの税率が軽減されるため、税負担が大きく異なります。 死因贈与は、財産を引き継ぐための柔軟な手段ですが、その選択には十分な検討が必要です。特に税金や契約書作成の重要性については弁護士に相談したうえで、トラブルの防止に努めるようにしてください。死因贈与は相続税の課税対象

- 死因贈与の税制上の取り扱いとは?
- 死因贈与は贈与税ではなく相続税の対象となる
死因贈与をする場合、税金はどのようにかかるのでしょうか?
死因贈与は、贈与税ではなく相続税の対象となります。
また、死因贈与で財産を取得する場合には、遺産全体の申告手続きを行う必要があります。これは、対象となる財産だけでなく、他の遺産も含めた遺産全体について、法定相続人全員で協力しながら進める手続きとなります。これにより、贈与税の申告とは異なり、手間がかかることがあります。
さらに、死因贈与によって不動産を受け取る場合、不動産取得税が課されます。 この税額は、原則として固定資産税評価額の4%です。一方で、法定相続人が遺贈により不動産を取得する場合、相続を原因とするため不動産取得税は非課税です。そのため、死因贈与を選択した場合、遺贈と比べて法定相続人の税負担が増えることになります。 また、不動産の名義変更に伴う登録免許税の税率も、遺贈と死因贈与で差があります。法定相続人が遺贈による相続登記を行う場合、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。しかし、法定相続人以外の遺贈や死因贈与に基づく登記では、税率が2%となります。死因贈与・遺贈のどちらを選ぶべき?

- 死因贈与を選択すべき場合とは?
- 遺贈を選択すべき場合とは?
死因贈与と遺贈のどちらにすべきか悩んでいます。
ここでは、死因贈与にした方が良い場合と遺贈にした方が良い場合について解説していきます。
死因贈与にした方が良い場合
死因贈与にした方が良いのは、以下のような場合が考えられます。【介護などの負担を担ってほしい場合】
負担付死因贈与を利用することで、受贈者に特定の義務を課すことができます。
贈与者は、介護などの具体的な負担内容を確実に履行してもらえる安心感を得られ、受贈者はその義務を果たすことで財産を確実に受け取ることができます。
【財産を取得してくれそうな場合】
遺贈では、受け取り手がその財産を望まない場合に相続放棄される可能性があります。一方、死因贈与は事前に受贈者の同意を得る必要があるため、財産を確実に引き継いでもらえます。
遺贈にした方が良い場合
上記に対して、以下のような場合では、遺贈を選択する方が適切でしょう。【亡くなるまで財産を家族に知られたくない場合】
遺贈では、財産の内容を受け取る人に伝える必要がなく、家族や他の方に知られずに遺言を作成できます。これは死因贈与にはないメリットです。
【相続人に不動産を渡したい場合】
法定相続人に不動産を渡す場合、遺贈は死因贈与に比べて税負担が軽くなります。不動産取得税や登録免許税の違いが主な理由です。特に、税負担を最小限に抑えたい場合は遺贈が適しています。
まとめ
死因贈与とは、贈与する側が亡くなった場合に贈与の効力が発生する贈与契約の一種で、遺産をあげる側ともらう側の合意が必要となります。そのため、家族との話し合いが必要となり、相続税の対象となります。死因贈与を選択すべきか、遺贈を選択すべきかについては、メリットとデメリットを比較して、ケースバイケースの判断となります。 死因贈与を検討されている方は、事前に相続の専門家である弁護士に相談したうえで、スムーズにご家族に財産が承継されるように準備をしておくことが重要でしょう。当事務所には、相続問題に詳しい弁護士が在籍しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.29相続放棄・限定承認空き家を相続する際の話し合いのコツを確認
- 2025.10.29相続全般親が経営していた賃貸マンション・アパートを相続したときの手続きなど解説
- 2025.10.20相続手続き代行【タイプ別】遺産相続における寄与分の計算方法をわかりやすく解説
- 2025.09.22相続全般相続の寄与分と遺留分の関係を解説!トラブル防止のポイントも紹介