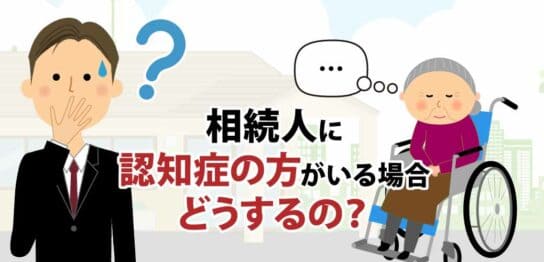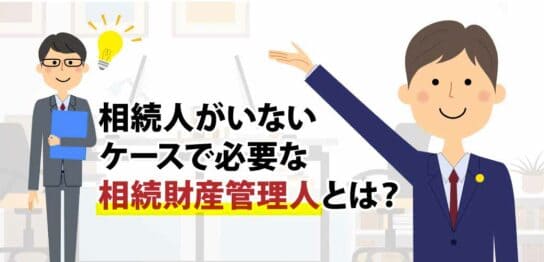はじめに
しかし、正式な遺産分割協議を経ずに長男が財産を勝手に処分したり、自分だけの判断で使い始めたりすると、他の相続人との間で深刻なトラブルに発展することがあります。
本記事では、長男による「相続の独り占め」によって起こりうるトラブルの具体例と、それに対する有効な対応策について、わかりやすく解説します。
「長男が遺産を全て相続すると主張して困っている」、「遺産を使い込まれてしまっている」といったトラブルを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
遺産相続で長男のみが遺産を独占できるパターン
そもそも、長男だけが遺産を独り占めするということは可能なのでしょうか・ここでは、長男が遺産を独り占めできるパターンとして、以下3つを紹介します。
- 相続人が長男のみ
- 遺言書で長男のみ相続させるとしていた
- 遺産分割協議で長男のみが相続すると協議した
それぞれについて、詳しくみていきましょう。
相続人が長男のみ
まず、法定相続人が長男のみである場合には、相続においても長男が遺産を独占することになります。
例えば、内縁の妻との間に子ども(長男)が1人いるような場合、内縁の妻は相続人とならないため、長男だけが相続することが可能です。
なお、内縁の妻などの相続人ではない身内がいる場合は、特別寄与料の請求をすることができますが、遺産自体は長男が独占をして、その長男に対して金銭の請求をする形になります。
長男だけに相続させる内容の遺言書がある
被相続人が遺言書で長男のみに相続させると指定していた場合も、長男が遺産を独占することになります。
遺言がある場合には、民法の相続の規定にかかわらず、遺言のどおりに相続を行うのが通常です。
ただし、長男だけに遺産が相続されたことによって、他の相続人の遺留分を侵害する場合、長男以外の相続人は長男に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺産分割協議で長男のみが相続すると協議した
相続人が複数いる場合にでも、遺産分割協議で長男のみが相続すると決めた場合は長男が遺産を独占することができます。
共同相続人がいる場合には法定相続分が民法で定められていますが、これはあくまで遺産分割における目安であり、特定の相続人だけに相続させることを禁止しているものではありません。
そのため、共同相続人が長男の遺産の独占を認めているのであれば、長男が遺産を独占できるのです。
遺言書で長男のみに相続させるとした場合のトラブル
被相続人が「長男だけに相続させる」という内容の遺言書を作成している場合、長男だけが遺産を全て相続することができます。
ただし、この場合は遺留分の扱いや遺言の効力について相続人の間でトラブルになりやすいので注意が必要です。
ここでは、遺言によって長男に遺産を独り占めされた場合の遺留分の扱いや、遺言の効力について詳しく解説します。
他の相続人から長男に対して遺留分侵害額請求をされる可能性がある
遺言自由の原則は、被相続人の意思を尊重するという観点から認められているものですが、他方で残された相続人の生活保障や被相続人の財産の維持形成に貢献した相続人に対する潜在的持分の清算という相続制度全体の観点から、遺言自由の原則は一部制限されています。
その制限の一つとして挙げられるのが、相続人の「遺留分」です。
遺留分とは、相続人が相続によって最低限の財産を得られる権利のことで、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が保障されています。
被相続人が行った生前贈与や遺言によって遺留分を侵害された場合、遺留分を侵害された相続人は、生前贈与された人や遺産を受け取った人に対して遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いを請求可能です。
この手続きを遺留分侵害額請求といいます。
つまり、長男だけに相続させる遺言書があった場合でも、長男以外の相続人(被相続人の兄弟姉妹以外)は、長男に対して遺留分侵害額請求ができるということです。
遺言書の無効を主張される可能性がある
長男だけに相続させるなど、相続人の間に大きな不均衡が生じるような遺言書がある場合、遺言書によって不利な扱いを受けた相続人が遺言書の無効を主張する可能性があります。
例えば、遺言書は偽造されたものである、あるいは被相続人は認知症で遺言書を作成する能力がなかったなどの理由から無効であるとして、訴訟を起こすことも可能です。
遺産分割で長男だけが相続すると主張した場合に発生するトラブル
遺言書がない場合、相続人の話し合いで遺産の分け方を決めることになります。
しかし、この段階で長男が遺産を独り占めしようとすると、話し合いがまとまらずにトラブルになるおそれもあるでしょう。
ここでは、遺産分割で長男が遺産を独り占めしようとしたときに生じやすいトラブルと、その対処法を紹介します。
他の相続人の同意が得られず遺産分割がすすまない
遺言書がない場合、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めなければなりません。
遺産を分け合うことを遺産分割、全員で話し合うことを遺産分割協議と呼びます。
民法では、遺言書がない場合に相続人が遺産を相続する割合(法定相続分)が定められているため、通常の遺産分割協議では、この法定相続分を基準に遺産を分け合うことが多いです。
そして、遺産分割協議は、相続人全員の同意をもって初めて成立します。
しかし、遺産分割協議において、被相続人の長男が「自分が遺産を全て相続する」と主張した場合、いつまでも話し合いがまとまらず、遺産分割を完了できないリスクが生じるでしょう。
この場合、調停や審判など、より複雑な手続きを経て遺産分割の方法を決めなければなりません。
調停・審判を行えば「長男だけが相続する」ことは阻止できる
長男が「遺産を全て相続する」と主張し、遺産分割協議がまとまらない場合、調停や審判を行う必要があります。
調停とは、裁判官と調停委員で構成される調停委員会が当事者の間に入り、裁判所において話し合いをする手続きです。
第三者が間に入ることで、全員が納得できる着地点を探せるのがメリットですが、ここでも長男が「自分だけが遺産を相続する」という主張を崩さない場合は、調停での合意は難しいでしょう。
そして、調停で合意ができない場合は、審判に移行します。
審判では、当事者から提出された資料や首長内容をもとに、最終的に裁判官が遺産の分け方を決めます。
その際、遺産の分け方の基準となるのは法定相続分なので、長男だけが相続をするという分け方になることはまずありません。
このように、遺言書がないのに長男が自分だけが相続すると主張したとしても、その主張が認められる可能性は低いでしょう。
「遺産を全て相続する代わりに親の面倒をみる」という約束を反故にされる
遺産分割で長男だけに相続させる場合に起きやすいのが、「親の面倒をみる」という条件で全ての遺産を相続したにもかかわらず、その約束を反故にする、というトラブルです。
遺産分割の際、長男が遺産を独占するために「親の面倒をみる」という条件を提示することがあります。
特に、長男が被相続人と同居しており、配偶者が相当高齢であるような場合にこのような主張をされることが多いです。
しかし、このような場合長男が約束を反故にしたり、事情があって面倒をみられなくなったりすることも少なくありません。
さらに、長男が遺産を隠すなどして遺産分割で適切な判断をできなくするようなおそれもあります。
そのため、遺産相続では平等に遺産を分けつつ、親の面倒をみることについては別で取り決めをするなどして対処するのがよいでしょう。
遺産を独り占めされてしまった場合にすべきこと
長男など、相続人の一人が遺産を独り占めしようとしている、もしくは既に遺産を独占している状況の場合、どうすればよいのでしょうか。
以下では、その対処法について解説します。
被相続人の銀行口座を凍結する
長男が遺産を独占している場合、まずは被相続人の銀行口座を凍結しましょう。
被相続人が亡くなると、通常銀行は権利者以外からの引き出しに応じないために預貯金口座を凍結します。
しかし、銀行は利用者が亡くなったことを自動的に知れるわけではありません。
そのため、キャッシュカードを持っていて、暗証番号を知っているような相続人がいる場合、速やかに銀行に連絡して口座を凍結しなければ、お金を独り占めされてしまう可能性があります。
したがって、被相続人が亡くなったら、すぐに銀行に被相続人が亡くなったことを連絡しましょう。
なお、場合によっては、被相続人死亡の戸籍謄本・住民票の除票などを要求されることがあります。
取引履歴を調べて使い込みの有無を判断する
長男が遺産を独占している可能性がある場合、被相続人の銀行の通帳を確認して死亡日以後に引き出された金銭がないかを調べましょう。
銀行の通帳が確認できなければ、銀行に問い合わせて取引履歴を開示してもらうこともできます。
また、自宅にある現金や貴金属などの高級品が残っているかも確認してみましょう。
使い込まれた分を取り戻すために話し合う
既に遺産が独り占めされている場合、使い込まれてしまった分を取り戻しましょう。
単に使い込んだ旨を指摘するのではなく、使い込んだことやその金額を証明できる書類を用意し、話し合いの場を設けるようにしてください。
話し合いで解決できない場合は弁護士に相談する
遺産の独り占めや使い込みについて、話し合いで解決できない場合には、弁護士に相談して訴訟や相手の財産の保全などについて、判断を仰ぎましょう。
なお、遺産を使い込まれている場合は、証拠の確保や相手の財産の保全をスピーディーに行う必要があります。
そのため、遺産の使い込みが発覚した時点で、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
不動産を長男が独り占めしている場合は、遺産分割で考慮する
預貯金などの財産のほかに、長男だけが不動産を独り占めしている場合もあるでしょう。
例えば、被相続人と長男が同居しており、被相続人が亡くなったことによって長男だけがそのまま居住しているような場合です。
この場合、遺産分割が終わるまでは不動産は共有であるというのが法律上の規定であり、長男が不動産を使用すること自体には問題は生じません。
しかし、不動産が共有財産である以上、他の相続人も同様に使用・収益をすることができる状態のため、長男のみが不動産を独占している場合は他の相続人の権利を侵害することになります。
そのため、そのまま長男が不動産を独占し続けることを主張した場合は、遺産分割の際に賃料に相当するような額を考慮する必要があるでしょう。
遺産の独り占めを弁護士に依頼するメリット
遺産の独り占めが発覚した場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
遺産の独り占めについて、弁護士に相談するメリットは、以下のとおりです。
- 遺産分割協議での交渉を任せられる
- 遺産分割協議書の作成や相続手続きがスムーズになる
それぞれのメリットについて、詳しくみていきましょう。
遺産分割協議での交渉を任せられる
遺産を独り占めについて弁護士に相談・依頼すると、相手との遺産分割協議の交渉を任せられます。
遺産を独り占めする相手がいるような場合、遺産分割の対象となる遺産の額や使い込んだ分の取り戻しなどを交渉したうえで、遺産分割協議をまとめなければなりません。
そして、遺産を独り占めするような人と交渉をするわけですから、お互いが対立しやすく精神的な負担は免れないでしょう。
しかし、弁護士に依頼すると、弁護士が代理人として交渉するため、依頼者本人が面と向かって交渉をする必要はなく、精神的な負担は少なくすむでしょう。
遺産分割協議書の作成や相続手続きがスムーズになる
弁護士には、遺産分割協議がまとまらずに調停・審判をする場合はもちろん、遺産分割協議がまとまった際の遺産分割協議書の作成や、その後の相続手続きまで全てを任せることができます。
遺産分割協議書の作成や相続手続きには、様々な専門知識が必要になるので、弁護士に任せることでスムーズに進められるでしょう。
遺産を独り占めされないために事前にしておくべきこと
遺産を独り占めされないためには、相続の際に相続人の間でしっかり話を行うことも大切ですが、何よりも被相続人の生前に事前に対策しておくことが重要です。
具体的には、以下のような対策をしておくとよいでしょう。
・ 家族の関係を良好にする
・ 遺言書を作成する
相続について事前に話し合っておけば、遺産の全容を相続人全員が確認することができるので、そもそも独り占めして使い込むということが難しくなるでしょう。
また、いざ相続が発生したときに、遺産を一人が独占しないように、家族の関係を良好にしておくことも大切です。
どうしても不安がぬぐえない場合は、法的な方法として遺言書の作成も検討しましょう。
既に長男に独り占めさせている遺言書がある場合に撤回は可能?
被相続人となる方がまだ亡くなっておらず、既に既に長男に遺産を独り占めさせる内容の遺言書を作成したものの、被相続人となる方がまだなくなっていない場合は、遺言の撤回が可能です。
民法1022条では、遺言の方式で遺言書の撤回をすることができる旨を規定しています。
また、作成した遺言書の内容と異なる遺言をするような場合や、遺言の目的となっているものを処分したような場合には、前の遺言書を撤回したもとみなす規定もあります。
そのため、既に既に長男に独り占めさせている旨の遺言書がある場合には、その遺言書を撤回する旨の遺言書を作成したり、新たな遺言書で前の遺言書と抵触する内容の遺言書を
作成したりすることで遺言書の撤回が可能です。
まとめ
通常、相続人が長男のみといった特殊な場合を除いて、長男が遺産を独り占めすることはできません。
仮に長男だけに相続させるといった内容の遺言書があったとしても、他の相続人は遺留分侵害額請求をすることができるので、長男が何の負担もなしに遺産を独占することはできないでしょう。
相続において、他の相続人が遺産を独り占めしようとしている場合には、きちんと自分の権利を主張する必要があります。
自身で対応するのが難しい場合には、相続に詳しい弁護士に相談し対応を検討するとよいでしょう。

- 遺産相続でトラブルを起こしたくない
- 誰が、どの財産を、どれくらい相続するかわかっていない
- 遺産分割で損をしないように話し合いを進めたい
- 他の相続人と仲が悪いため話し合いをしたくない(できない)
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.11.26相続放棄・限定承認山林の相続、手続きを放置するとどうなる?デメリット・対処法を解説
- 2025.09.25相続放棄・限定承認代襲相続と相続放棄の関係について解説
- 2025.09.25相続手続き代行未支給年金は相続放棄をしても受け取れる!相続放棄のルールの確認とともに解説
- 2025.08.22遺産分割協議遺産分割調停の必要書類について解説