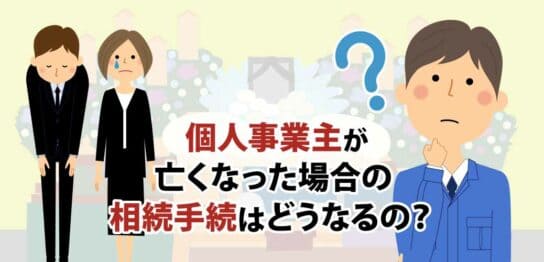- 不動産の相続で兄弟姉妹がもめる原因とは?
- 兄弟姉妹が相続した不動産を分割する方法とは?
- 不動産の相続をスムーズに進めるポイントとは?
【Cross Talk 】兄弟姉妹が不動産を相続した場合、どのように分ければいいのでしょうか?
親の実家を兄弟姉妹で相続した場合、どのように分ければいいのでしょうか?
相続不動産の分け方としては、現物分割や、換価分割、代償分割などの方法があります。
不動産を兄弟姉妹で相続した場合について、詳しく教えてください。
親が亡くなり実家を兄弟姉妹で相続したものの、「どう分ければいいかわからない」、「兄弟間で意見が食い違って話し合いが進まない」という場合、どうすればいいのでしょうか。 この記事では、不動産の相続で兄弟がもめる主な原因や、兄弟で不動産を円満に分ける具体的な方法、そしてトラブルを未然に防ぎ、スムーズに進めるためのポイントについて、弁護士が解説していきます。
不動産の相続で兄弟がもめる原因

- 不動産の相続で兄弟姉妹がもめる原因とは?
- 不公平な相続はもめる原因になる
不動産を相続する場合、なぜ兄弟姉妹がもめるのでしょうか?
ここでは、不動産相続で兄弟姉妹がもめる原因を解説していきます。
遺言書がない
遺言書がない場合、故人の財産は遺産分割協議によって分け方を決定します。この際、法定相続分が目安となりますが、不動産、特に土地は物理的に分けることが難しいため、公平な分割が困難になりがちです。 例えば、実家が一つしかない場合、誰がその家を相続するのかで意見が対立しがちです。また、複数の土地があっても、それぞれの評価額や利用価値は異なるため、均等に分けるのは至難の業です。 そのため、遺言書があれば、故人の意思が明確になるため、不公平に見える分割であっても、それに従わざるを得ず、結果としてトラブルが回避される可能性が高まります。関連記事:遺言書を紛失した場合にはどう対応すればいいか?
想定よりも現金が減っていた
親が亡くなった時点で、想定よりも現金が減っており、遺産が不動産しかないという場合にも、トラブルになる可能性があります。 例えば、長男が実家である土地・建物を相続してしまうと、他の兄弟姉妹が受け取れる遺産がないため、不満の原因になる可能性があります。また、親の現金が減った要因として、兄弟姉妹による使い込みが疑われる場合も、相続トラブルになり得ます。キャッシュカードと暗証番号があれば、誰でも預金を引き出せるため、親の面倒を見ていた兄弟姉妹が、「遺産である現金を浪費や着服したのではないか?」と疑わざるを得ない場合もあるでしょう。 このように遺産の中の現金が想定よりも減少しており、不動産しかない場合には、兄弟姉妹がもめる原因になります。生前贈与があった
親の生前に、一部の兄弟に対して、マイホームの購入資金や土地などの特定の財産が贈与されていた場合、これは特別受益とみなされ、トラブルの原因となることがあります。特別受益とは、一部の相続人だけが特別な利益を受けていた場合の利益のことをいい、遺産の前渡しと考えられています。そのため、特別受益を受けた相続人の相続分は減額され、他の兄弟の取り分が増えるように調整されるのが原則です。 しかし、何が生前贈与にあたるのか、その金額はいくらだったのか、といった判断が非常に難しく、特別受益を主張する側がその事実や金額を証明しなければならないため、話し合いがまとまらず、争いに発展しやすい傾向にあります。関連記事:相続対策に遺言と生前贈与はどちらが良いのか
介護などの負担によって寄与分を主張している
親の財産維持や増加に無償で貢献した相続人は、その貢献度に応じて、他の兄弟よりも多めに相続できる寄与分を主張できる場合があります。例えば、親の介護を長期間にわたって献身的に行っていた、親の事業を手伝って財産を増やしたなどが該当します。 しかし、寄与分が認められるためには、民法に定める一定の要件を満たす必要があります。他の兄弟がその貢献を認めない場合や、相続財産が不動産に偏っているために具体的な分割方法で意見が割れる場合など、寄与分の主張が新たな争いの火種となることも少なくありません。兄弟で相続した不動産を分ける方法

- 兄弟が相続した不動産の分割方法とは?
- 現物分割、換価分割、代償分割などの方法がある
兄弟姉妹が相続した土地を分けるには、どのような方法がありますか?
ここでは、相続した不動産の分割方法について解説していきます。
現物分割(土地の分筆)
現物分割とは、相続する不動産をそのままの形で分ける方法です。土地の場合であれば、一つの土地を複数に区切り、それぞれの区画を兄弟が個別に相続する「分筆(ぶんぴつ)」がこれにあたります。現物分割(分筆)することで、兄弟がそれぞれ独立した土地を持つことができるため、将来的な利用や売却に関して他の兄弟の意向に縛られることがなくなります。また、分筆によって土地の評価額が下がり、固定資産税や都市計画税が低くなるというメリットがあります。
しかし一方で、分筆には測量費用や登記費用が発生し、まとまった出費が必要です。また、分筆の仕方によっては、それぞれの土地の利用価値や売却価格に差が出てしまい、不公平感が生じることもあります。さらに、建築基準法などの規制により、建物の建築や増改築が制限される可能性もあるため、慎重な検討が必要になります。換価分割
換価分割は、相続した不動産を売却し、その売却代金を兄弟間で分け合う方法です。金銭で明確に分けられるため、最も公平な遺産分割が実現できる、売却によってまとまった現金が入るため、相続税の納税資金を確保できるという点もメリットです しかし一方で、大切な不動産を手放すことになるため、故人との思い出の品として残したい場合には不向きです。売却には兄弟全員の同意が必要となるため、一人でも反対者がいると実行できません。また、市場価格よりも安値で売却せざるを得なかったり、譲渡所得税や仲介手数料などの諸費用が発生し、手元に残る金額が想定より少なくなったりなどのリスクもあります。関連記事:不動産の遺産分割方法の1つである換価分割をする際の3つのポイント
代償分割
代償分割とは、特定の相続人が不動産を単独で相続する代わりに、他の相続人に対して、その不動産の価値に応じた代償金を支払う方法です。これにより、不動産の所有権は1人の相続人に集約されつつも、他の相続人の取り分も確保できるため、公平性を保ちやすいという特徴があります。 不動産を単独名義で相続できるため、将来の管理や活用がスムーズになるでしょう。 しかし、代償分割を選択する場合には、不動産を相続する側に代償金を支払う経済力が必要不可欠です。また、不動産の評価方法や代償金の金額を巡って兄弟間で意見が対立し、トラブルに発展することもあります。関連記事:不動産相続の際の代償分割の要件や代償金の決め方などを解説!
共有分割
共有分割とは、不動産を売却せず、兄弟がそれぞれの持分に応じて共同で所有する方法です。例えば、法定相続分通りに、兄弟全員が同じ不動産の共有名義人となります。 一見公平に見えるこの方法ですが、デメリットが非常に大きい点が特徴です。例えば、不動産を売却する場合には、共有者全員の同意が必要となります。そのため、意見の相違から合意形成が難しく、結果的に不動産が売却できないということも少なくありません。 また、共有者の死亡によって次世代に相続が発生すると、共有持分がさらに細分化され、権利関係が複雑になり、将来的な売却や管理がより一層困難になるリスクが高いです。相続放棄
相続放棄とは、相続人が故人の全ての財産を相続する権利を放棄することです。これには不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。 相続放棄をすることで、遺産相続に関する一切の関わりを断つことができ、特に故人に多額の借金があった場合など、負債を背負うリスクを回避できます。 しかし、相続放棄をすると、不動産や預貯金など、プラスの財産も一切相続できなくなります。また、相続放棄をするには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てる必要があります。この期限を過ぎてしまうと原則として認められず、たとえ借金があったとしても相続せざるを得なくなります。不動産の相続で兄弟がもめずに円満に進めるポイント

- 兄弟が不動産を相続した場合のポイントとは?
- 相続に詳しい弁護士に相談する
兄弟姉妹が不動産を相続する場合には、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?
ここでは、不動産の相続をスムーズに進めるためのポイントを解説していきます。
遺言書を作成しておく
相続トラブルを未然に防ぐ上で最も効果的なのは、被相続人が遺言書を遺しておくことです。遺言書には、誰にどの財産をどれだけ相続させるかという故人の明確な意思が示されるため、相続人同士の無用な争いを大幅に減らすことができます。 遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類が主ですが、紛失や偽造、内容の無効化といったリスクを避けるためには、公正証書遺言の作成を強くおすすめします。公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与し、証人の立会いのもとで作成されるため、法的に有効と認められる可能性が高く、また内容の確実性も担保されます。さらに、原本が公証役場で保管されるため、紛失の心配もありません。関連記事:秘密証書遺言の作成方法やメリット、開封方法などについて解説!
遺産分割協議を実施する
遺言書がない場合や、遺言書があっても全ての財産について指定がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議が必要です。 遺産分割協議を行う際には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家が間に入ることで、感情的になりがちな話し合いを客観的に見つめ直し、冷静な判断を促すことができます。 合意に至った内容は、遺産分割協議書として書面に残し、紛争が蒸し返されないようにしておくことが重要です。まとめ
不動産の相続は、現金のように分けられない特性から、兄弟間でのトラブルに発展しやすいデリケートな問題です。遺言書がないことや、生前贈与があること、介護などの寄与分の主張などが主な争いの原因となります。 こうしたトラブルを避けるためには、遺言書の作成、不動産の適切な評価と分割方法の選択(現物分割、換価分割、代償分割など)、そして兄弟間での遺産分割協議が不可欠です。 当事務所には相続問題に詳しい弁護士が在籍しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.11.26相続税申告・対策相続税の納税義務者とは?種類や該当する方について
- 2025.10.29遺言書作成・執行遺言についての相談を上手にするコツを紹介
- 2025.10.29成年後見相続人に認知症の方がいる場合どうするの?成年後見人制度とは?
- 2025.10.20相続全般相続した不動産を兄弟で分ける方法!兄弟間で揉める原因と円満に進めるポイント