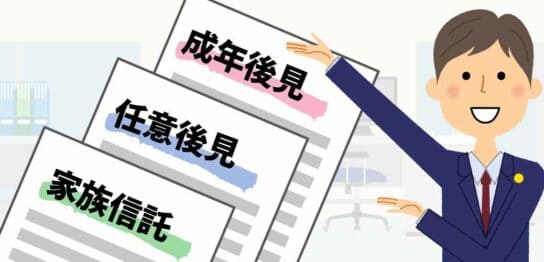親が認知症などを患い、成年後見制度を利用しようとしたとき、親の兄弟から同意を得られずに悩んでしまうケースは少なくありません。
なかには「親族の協力が得られないと申立てが難しいのでは…」と不安になる方も多いでしょう。
しかし、成年後見制度では、同意書が無くても申立てが可能です。
本記事では、成年後見制度における同意書の役割や、同意書を書いてもらえないときの対処法などについてわかりやすく解説します。
なかには「親族の協力が得られないと申立てが難しいのでは…」と不安になる方も多いでしょう。
しかし、成年後見制度では、同意書が無くても申立てが可能です。
本記事では、成年後見制度における同意書の役割や、同意書を書いてもらえないときの対処法などについてわかりやすく解説します。
目次
成年後見の申立てをするのに兄弟が同意書(意見書)を書いてくれない
成年後見の申立てにおいて、本人の兄弟の同意書(意見書)は必須ではありません。
そもそも、成年後見制度において、親族の同意は申立ての要件とはされていません。
家庭裁判所では、後見等の申立ての際に親族の同意書の添付を求めているため、必須と勘違いする方も多いですが、同意書は被後見人となる本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるか」や、「成年後見人の候補者が本人保護のためにふさわしい人かどうか」を判断するための材料にすぎません。
兄弟を含む親族の同意書がないからといって成年後見の申立てができないことはないので、安心してください。
成年後見の申立てに兄弟が同意しない理由とは
成年後見は、被後見人を守る目的でおこなわれるため、「被後見人の兄弟が成年後見に同意しない」というのは一見不自然に思える方もいるでしょう。被後見人の兄弟が成年後見に反対する主な理由としては、被後見人が精神上の問題を抱えていることを隠したいケースが挙げられます。
成年後見の申立てをする場合は、本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」という状態であることが必要です。
認知症や精神疾患などでこのような状態になる人が多いのですが、被後見人の親族のなかには、被後見人がこのような状態にあることを隠したいと考える人も多く、同意をしてもらえないケースもあるのです。
兄弟が同意書(意見書)をくれなさそうな場合の注意
兄弟が同意書を書いてくれない場合でも、成年後見の申立ては可能です。しかし、同意書なしで申立てを行う際は、以下のようなポイントに注意しなければなりません。
・鑑定をする可能性がある
・後見人について意見をする可能性がある
以下では、それぞれの注意点について、詳しく解説します。
鑑定をする可能性がある
同意書を書いてくれない親族がいる場合、家庭裁判所は同意をしなかった親族に意見を求めることになります。ここで、兄弟に「本人は認知症(もしくは、精神疾患)ではない」と主張されると、申立ての際に医師の診断書が添付されていても、家庭裁判所としても本人の状態を詳しく調べる必要があります。
そして、裁判所は本人の状態を確認するために「鑑定」という手続きを行うことになるのです。
鑑定とは、裁判所が本人について「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」かどうかを判断するために、選任された医師が本人の状態を確認する手続きのことです。
この手続きが発生すると、10万円程度の費用がかかることになるため、同意書がある場合の申立てと比べると費用負担が増えることになります。
そのため、兄弟などの親族が同意書を書いてくれないような場合には、追加費用が発生することなどを伝えて交渉するのもよいでしょう。
後見人について意見をする可能性がある
後見人に就任してもらう人があらかじめ決まっている場合には、後見人就任予定者として指定したうえで申立てを行います。申立ての際に同意書がない場合、この後見人就任予定者が適切かどうかに対して、同意していない後見人が意見をしてくることがあるでしょう。
例えば、親族がそのまま後見人になろうとしている場合に「自分のほうが適切だ」と主張したり、専門家に依頼しようと思っている場合に「そんな部外者に任せられない」と主張してきたりすることがあります。
後見人は本人のために選ばれるものなので、その人が適切であることや、今まで親族が申立てに反対してきた経緯なども伝えて、申立ての際に指定した候補者が適切であることを家庭裁判所に伝えられるようにしましょう。
さいごに|兄弟の同意書がなくても申立ては可能!
このページでは、成年後見の申立てをするのに兄弟が同意書(意見書)を書いてくれない場合について解説しました。
同意書がなくても申立てはできるものの、反対する人がいることによって、家庭裁判所が審判をする際により慎重になることが考えられます。
このような場合には、弁護士に相談・依頼して、スムーズに成年後見を申立てられるようにしましょう。
遺言や相続でお困りの方へ

分からないときこそ専門家へ
相続については、書籍やウェブで調べるだけではご不安な点も多いかと思います。当事務所では、お客様の実際のお悩みに寄り添って解決案をご提案しております。「こんなことを聞いてもいいのかな?」そう思ったときがご相談のタイミングです。

- 判断力があるうちに後見人を選んでおきたい
- 物忘れが増えてきて、諸々の手続きに不安がある
- 認知症になってしまった後の財産管理に不安がある
- 病気などにより契約などを一人で決めることが不安である
初回相談
無料
無料
法律問題について相談をする
この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.05.23相続全般相続人代表者指定届とは?その効力は?書き方も併せて解説
- 2024.03.22相続放棄・限定承認遺留分放棄とは?相続放棄との違いやメリット、撤回の可否を解説!
- 2023.11.06相続全般「死んだら財産をあげる」相続における口約束はトラブルのもと!事例をもとに解決方法を解説
- 2023.07.18遺言書作成・執行遺言書を紛失した場合にはどう対応すればいいか?