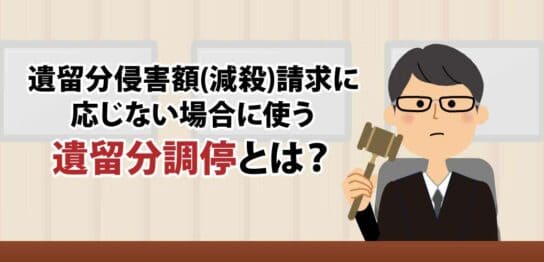- 遺留分侵害額請求自体を拒否する制度はない
- 請求された金額が不当な場合は、金額を争うことはできる
- 支払いを拒否するのではなく、分割払いなどを提案すべき
【Cross Talk 】遺留分侵害額請求をされたら拒否しても大丈夫?
私は長男で、家業を継ぐために父の遺産を多く相続しました。ところが、遺留分を侵害されたとして、弟から遺留分侵害額請求をされてしまったのです。請求を拒否しても大丈夫ですか?
遺留分は法律で認められた正当な権利なので、遺留分侵害額請求を拒否する制度はありません。単に拒否をすると裁判になる可能性があるので、分割払いなどを提案して対処しましょう。
遺留分侵害額請求を拒否することはできないんですね。遺留分侵害額請求のトラブルを防ぐコツがあれば教えてください!
被相続人の配偶者や子どもなど、一定の相続人には遺留分が認められます。 遺留分を侵害した場合、遺留分に相当する金額を支払うように請求されることがあります。 遺留分侵害額請求をされた場合は、単に支払いを拒否すると裁判を起こされるリスクがあるので、適切な対処をすることが重要です。 そこで今回は、遺留分侵害額請求を拒否できない仕組みや対策について解説いたします。
遺留分侵害額請求は拒否できない

- 遺留分侵害額請求自体を拒否する制度はない
- 請求された金額が不当な場合は、金額を争うことはできる
私と同じく相続人である弟に、遺留分侵害額請求をされたのですが、請求を拒否する方法はありますか?
遺留分侵害請求は法的に正当な請求であり、請求自体を拒否する制度はありません。ただし、請求された金額が不当な場合は、金額を争うことはできます。
遺留分とは
遺留分とは、 一定の相続人について法律で認められている、遺産の最低限の取り分を取得する権利のことです。 被相続人が亡くなって相続が発生すると、配偶者や子どもなどの相続人は、被相続人の遺産を相続することを期待するのが一般的です。 しかし、相続人でない方に対して全ての遺産を譲ることを遺言書で指定するなど、場合によっては、本来得られたはずの遺産を相続できなくなる場合もあります。 相続人が遺産を相続できなくなると、期待していたはずの遺産を得られないだけでなく、その後の生活に悪影響が生じる可能性も少なくありません。 そこで、一定の相続人について、遺産の最低限の取り分の取得を認めることにしたのが、遺留分の制度です。 遺留分を請求する権利を有する相続人のことを、 遺留分権利者といいます。 自分の遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分を侵害した相手に対して、遺留分に相当する金額の支払いを請求することができ、これを遺留分侵害額請求といいます。遺留分侵害額請求自体を拒否できない
遺留分侵害額請求をされた場合、 請求自体を拒否することはできません。 遺留分は法律によって定められた権利であり、正当な遺留分侵害額請求を拒否する制度は存在しないからです。 遺留分侵害額請求をされた場合に、お金がないから払えないなどといって拒否をしてしまうと、相手に訴訟を起こされて裁判になる可能性があります。 もし裁判になった場合、訴訟に応じるための費用や手間がかかるので、請求を拒否した際には想像もしなかった負担が生じる可能性があります。 詳しくは後述しますが、遺留分侵害額請求をされた場合は拒否するのではなく、無理なく支払える方法を探ることが重要です。金額が不当な場合は争える
遺留分侵害請求の 金額が不当な場合は、金額について争うことが可能です。 遺留分侵害請求自体を拒否することはできませんが、それはあくまで正当な遺留分の金額を請求している場合です。 遺留分として請求されている金額が不当な場合は、その金額について争うことができます。例えば、遺留分侵害額請求として1,000万円を請求されたものの、正当な遺留分侵害額を計算すると800万円である場合、差額の200万円については、根拠のない不当な請求であるとして争うことが可能です。
ただし、適正な遺留分侵害額の部分については正当な権利行使であるので、800万円の部分については、原則どおりに支払う義務があります。 適正な遺留分侵害額を算出するには、一定の期間内の生前贈与や特別受益を相続財産に含めるなど、複雑な計算が必要な場合もあるので、場合によっては弁護人に相談するのがおすすめです。遺留分を拒否した場合に起こること
内容証明が送られてくる
遺留分を拒否した場合、通常は遺留分権利者から遺留分侵害額を請求する内容証明郵便が送られてきます。
遺留分侵害額請求の行使方法については特に規定がないのですが、遺留分侵害額請求には相続の開始及び自身の遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内に行使しなければならないという期間制限があるので、期間内に権利行使した証拠を残すために、配達証明付きの内容証明郵便によって請求するのが一般的です。
調停・裁判が起こされる
内容証明郵便を受け取った後も遺留分侵害額の支払いを拒否すると、遺留分権利者から裁判所における法的手続をとられることになります。
裁判所における法的手続には、調停と裁判(訴訟)の2種類があります。
遺留分侵害額請求については、原則としてまず調停を行い、調停で解決できなかった場合に訴訟を起こすことができるとされています。これを調停前置主義といいます。
裁判所における調停は、裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会を介して、申立人と相手方が話し合いを行い、合意の成立を目指す、というものです。
調停委員が、当事者双方の主張を整理したり、資料の提出を求めたりしてくれるので、当事者だけで話し合いをする場合と比べると、円滑な話し合いができます。
ただし、あくまでも話し合いですので、常に当事者間で合意が成立するとは限らず、合意が成立する見込みがない場合、調停は不成立で終了します。
調停が不成立になった場合、遺留分権利者は、遺留分侵害額を請求する訴訟を起こすことができます。
訴訟では、当事者の主張立証をもとに、裁判所が遺留分侵害額請求を認めるか否かの判決を下します。
判決が確定した場合、遺留分侵害に対する裁判所の判断を覆すことはできません。
強制執行が行われる
遺留分侵害額の支払いを認める判決が確定した後もその支払いを拒んだ場合、遺留分権利者から確定判決に基づいて強制執行を受けるおそれがあります。
強制執行とは、裁判所によって確定判決等の内容を強制的に実現する手続きのことです。確定判決の内容が金銭の支払いを命じるものである場合、支払いを命じられた方の財産(たとえば不動産)を差し押さえ、競売にかけて代金の中から弁済を受けたり、預貯金債権を差し押さえて自分の債権にしてもらい(転付命令といいます)、直接金融機関から弁済を受けたりすることができます。
このように、遺留分侵害額請求を拒むと、最終的には裁判所における手続によって遺留分侵害額請求の結果が実現することになります。
そのため、遺留分侵害額を請求された場合は、単に拒否するだけではなく、適切な対策が必要です。
遺留分侵害額請求を拒否できる場合

- 遺留分には時効がある
- 生前贈与がある場合、遺留分侵害がないこともある
- 相続人としての資格が認められない方には遺留分もない
遺留分が正当な権利だということはわかりましたが、どんな場合も絶対に拒否できないのでしょうか。
例外的に遺留分侵害額請求を拒否できる場合もあります。たとえば、遺留分侵害額請求権について時効が完成しているときです。また、生前に特別受益がある場合、遺留分を正しく計算すると遺留分侵害が認められないこともあります。さらに、相続欠格、廃除によって相続人の資格を失った場合、遺留分がなくなるので、遺留分侵害も認められません。
遺留分侵害額請求が時効になっている
遺留分侵害額請求には消滅時効があります。
具体的には、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間、その権利を行使しなかったときは、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅します。
また、遺留分権利者が遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったか否かにかかわらず、相続の開始から10年を経過したときも、遺留分侵害額請求権を行使することができなくなります。
そのため、遺留分権利者がこれらのいずれかに該当する場合は、遺留分侵害額請求を拒否することができます。
生前に特別受益がある
遺留分は、被相続人が相続開始のときに有していた財産の価額に、贈与した財産の価額を加え、債務を控除した額を基礎に計算します。
そのため、遺留分侵害を主張する方が被相続人の生前に贈与を受けていた場合(特別受益が認められる場合)、遺留分侵害が認められないときがあります。
具体例で説明しましょう。相続人は被相続人の子ども2人で、被相続人は唯一の財産である自宅の土地・建物(評価額3000万円)を長男に相続させる遺言を残しており、次男には数年前に現金1000万円を贈与していたとします。
遺言だけを見れば、全ての財産を長男が相続するので、次男の遺留分が侵害されているように思えます。
しかし、遺留分を算定するための基礎となる価額は、被相続人が相続開始のときに有していた土地建物3000万円に、次男に贈与した1000万円を加算した4000万円であり、次男の遺留分はその1/4にあたる1000万円となるので、生前贈与で1000万円を取得している次男は遺留分を侵害されていないということになるのです。
推定相続人の廃除をされている
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたり重大な侮辱を加えたりしたとき、または推定相続人に著しい非行があったときは、被相続人は推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できます。
家庭裁判所が廃除の請求を認めた場合、その推定相続人は相続人の資格を失うことになります。
遺留分は相続人に認められる最低限の権利ですので、相続人の資格がなくなれば遺留分もなくなります。
したがって、遺留分を主張する相続人が廃除されている場合、遺留分侵害額請求を拒否することができます。
相続欠格に該当している
民法は、相続人に一定の事由がある場合には相続人になることができないと規定しています。これを相続欠格といいます。相続欠格事由は、被相続人や先順位または同順位の相続人を故意に死亡するに至らせた場合や、遺言書を偽造、変造または隠匿した場合などで、不当な行為によって相続財産を得ようとした場合とイメージすればいいでしょう。
遺留分は相続人に保証された最低限の権利ですが、相続欠格に該当して相続人になることができない場合、遺留分も認められません。
したがって、遺留分侵害を主張する相続人に相続欠格事由がある場合、遺留分侵害額請求を拒否することができます。
遺留分侵害額請求が行われた場合に確認する3つのこと

- 本当に遺留分権利者にあたるか確認する
- 請求されている遺留分侵害額は適正か確認する
- 時効が完成していないか確認する
遺留分侵害額請求を拒否できる場合があるのなら、遺留分侵害額請求された場合、どうすればいいでしょうか。
まず、遺留分権利者にあたるとしても、請求された額が適正なものかを確認する必要があります。さらに、適正な額であったとしても、時効が完成してれば支払う必要がないので、時効が完成しているかどうかを確認する必要があります。また、遺留分侵害額を請求してきた方が本当に遺留分権利者にあたるかどうかを確認する必要があります。
請求者が遺留分権利者か
まず、請求者が遺留分権利者に該当するかどうかを確認します。
相続人であっても被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められません。
推定相続人が廃除されている場合や、相続欠格事由に該当する場合、相続人としての資格が認められなくなるので、遺留分権利者にもあたらないことになります。
遺留分侵害額請求権の時効が完成しているか
遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、あるいは、相続開始のときから10年間経過した後に遺留分侵害額請求権が行使された場合、時効が完成しているため、支払いに応じる必要はありません。
ですから、遺留分侵害額請求をされた場合、時効が完成しているか否かを確認する必要があります。
請求されている遺留分侵害請求の額
遺留分権利者からの請求であっても、その請求額が適正なものであるとは限りません。
遺留分権利者は通常、できるだけ多くの遺留分侵害額を請求したいと考えるでしょうから、自身が受けた特別受益を計算に入れていないとか、遺留分侵害額請求の相手方が取得する財産を高めに評価するといった方法で、適正な額よりも高額な請求をしてくる可能性があります。
ですから、遺留分侵害の請求額が適正なものかは必ず確認しなければなりません。
遺留分侵害額請求でトラブルにならないために

- 遺言書について話し合ったり、生命保険を活用したりなどの方法がある
- 支払いを拒否するのではなく、分割払いなどを提案すべき
遺留分侵害額請求でトラブルにならないためのポイントを教えてください。
遺留分侵害額請求のトラブルを防ぐには、遺言書や生前贈与について事前によく話し合っておくことが重要です。もし遺留分侵害額請求をされた場合は、単に拒否するのではなく、期限の延長や分割払いなどを提案しましょう。
遺言書や生前贈与についてよく話し合っておく
遺留分侵害額請求によるトラブルを防ぐには、 遺言書作成や生前贈与についてよく話し合っておくことが重要です。 ある相続人の遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する場合は、その相続人を含めて話し合っておくと、遺留分をめぐるトラブルの防止になります。 遺言書によって遺留分を侵害する結果になる場合は、なぜその内容で遺言書を作成するのかをきちんと説明しておかないと、あとでトラブルになる可能性が高いので注意しましょう。 例えば、長男が実家の家業を継ぐために必要なので、遺留分を侵害する結果になるとしても、遺産の大部分である実家の不動産を相続させなければならないなどです。 話し合いをしておけば必ずトラブルを防げるとは限りませんが、何も言わずに相続を迎えるよりも、相続トラブルを防止しやすくなります。 特定の相続人に生前贈与をする場合も、そのときの状況やタイミングによっては遺留分侵害額請求の対象になる可能性があるので、贈与をする前に事前に話し合っておきましょう。生命保険などの制度を利用できるようにしておく
遺留分侵害額請求のトラブルを防ぐための対策として、生命保険などの制度を活用する方法があります。 生命保険金は原則として遺留分の算定の基礎に含まれないことから、遺留分侵害請求の対象になりません。 ただし、生命保険を利用したとしても、保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に著しく不公平が生じる場合や、保険金の受取人が被相続人となっていた場合などは、例外的に遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。 そこで、生命保険を利用して遺留分対策をする場合は、事前に弁護人に相談することをおすすめします。すぐに払えないからと拒否するのではなく、分割払いなどのご提案を
遺留分侵害額請求をされて、経済的に支払う余裕がない場合は、 払えないからとすぐに拒否するのではなく、分割払いなどの提案をすることが重要です。 遺留分侵害額請求は法的な権利であり、拒否することはできません。これは請求された金額を支払う余裕がない場合も同様です。 支払う余裕がないからといって、相手の請求自体を拒否してしまうと、裁判所に訴訟を提起されて、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。 訴訟を起こされるリスクを回避するためには、相手の請求を拒否するのではなく、支払い期限の延長や分割払いなどを相手に提案することが重要です。 今は支払う余裕がなくても、少し待てば支払える金銭を確保できる場合は、支払い期限の延長を相手に提案すれば、金銭を確保してから支払うことができます。 一括で支払う余裕がない場合は、毎月無理なく支払える金額で分割払いを提案することも有益でしょう。 請求を拒否するのではなく、自分が無理なく支払える方法を相手に提案しましょう。まとめ
遺留分侵害額請求をされた場合、正当な請求に対して拒否できる制度は存在しないので、単に支払いを拒否することは得策ではありません。 支払い期限の延長や分割払いなど、無理なく返済できる方法を提案することが重要です。 ただし、請求された金額が不当な場合は、金額について争うことができます。 遺留分侵害額請求をされた場合に、対処法や金額を争う方法などを詳しく知りたい場合は、相続問題の経験が豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。

- 相手が遺産を独占し、自分の遺留分を認めない
- 遺言の内容に納得できない
- 遺留分の割合や計算方法が分からない
- 他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて困っている
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.29遺言書作成・執行公正証書遺言とは?作成の流れ・費用についてわかりやすく解説
- 2025.10.27遺産分割協議両親が離婚した・再婚するとどうなる?子どもが相続する場合の相続分について弁護士が解説
- 2025.10.27遺産分割協議相続人がいない場合に必要な相続財産清算人とは?
- 2025.04.18遺留分侵害請求遺留分侵害額請求を拒否できる?弁護士が解説