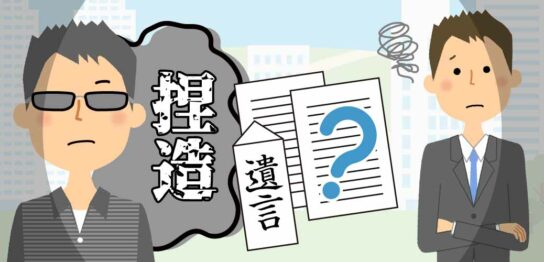正式な遺言とは
一般的に「遺言」と聞くと、故人が家族などに向けて自分の死後について希望を記した手紙などをイメージする方が多いでしょう。
しかし、実は遺言が「正式な遺言」として認められるには、いくつかの条件を満たさなければなりません。
ここでは、遺言が「正式な遺言」として認められるためのポイントを紹介します。
遺言は民法に規定された方法でしなければならない
民法では、「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない」とされており、それぞれの遺言には詳細な作成方法や書式が定められています。 つまり、民法が定めた方式通りの自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言でなければ、正式な遺言とは認められないのです。このように遺言について厳格な方式が定められているのは、遺言の効力が発生するのは遺言者の死亡時からと規定されており、効力発生時に遺言の内容である意思表示が遺言者の真意によるものであることを確証できるようにするためであるとされています。
ここからは、民法で定められている3つの遺言の種類について見ていきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名のとおり、遺言者自身が書く遺言書のことです。自筆証書遺言を作成する際は、原則として遺言者が全文、日付、氏名を書き、印鑑を押さなければなりません。
自筆証書遺言には、方式が簡単である、費用がかからない、遺言の存在や内容を秘密にすることができるといったメリットがあります。 一方で、専門家の関与なしに作成できるため、方式を誤ると遺言としての効力が認められない可能性があるというデメリットがあります。また、遺言の保管制度を利用していない場合、遺言を発見できない、相続人による遺言の破棄隠匿、消失などのリスクがあることも忘れてはいけません。
なお、自筆証書遺言については、近年大きな法改正が2つありました。
1つ目の改正内容は、相続財産の目録を自書する必要がなくなったことです。
これまではどれだけたくさん財産があっても手書きの財産目録を要求されていましたが、改正によってたのですが、署名押印があればパソコン等を使用して目録を作成してもよいことになっています作ってもいいことになったのです(目録に署名押印することは必要です)。
2つ目の改正内容は、自筆証書遺言の保管制度ができたことです。
これまで自筆証書遺言には、相続人が遺言書を発見できない、一部の相続人が遺言書を破棄・隠匿する、火災などによって滅失する、といったリスクがありました。
しかし、民法改正によって法務局が自筆証書遺言を保管する制度ができたことで、このようなリスクを回避することができるようになったのです。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公正証書(公証人という公務員が作成する文書)による遺言のことです。公正証書遺言の作成には、以下のような厳格な方式・作成方法が定められています。
・証人2人以上の立会いがあること
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
・公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること
・遺言者及び証人が、筆記が正確であることを承認した後、各自署名押印すること
・公証人が、その証書は上記4つの方式に従って作ったものであることを付記し、署名押印すること
公正証書遺言を作成する際はには、、公証人という専門家が関与するため、方式の誤りや記載ミスによって方式を欠いて遺言の効力が認められないという事態を防ぐことが可能です。また、公証役場で遺言の原本を保管するため、滅失等のリスクがない点もメリットといえます。
一方、公正証書遺言の作成には複雑な手続きが必要なこと、費用もかかること、証人に遺言の内容を知られることなどのデメリットも存在します。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま公証人及び証人に遺言書の存在を証明してもらう遺言のことです。秘密証書遺言の作成には、以下のような厳格な方式・作成方法が定められています。
・遺言者が証書に署名押印すること
・遺言者が証書を封じ、証書に押した印鑑で封印すること
・遺言者が公証人一人及び証人二人以上の前に証書を提出して、自己の遺言書であること並びに筆者の氏名及び住所を申述すること
・公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印すること
秘密証書遺言には、遺言内容を秘密にできる、署名以外は自筆でなくてもよい、変造(改ざん)を防げるといったメリットがあります。 一方、手続きが複雑で費用もかかること、専門家の関与がないため遺言内容が不明確なものになるおそれがあること、公証役場が原本を保管してくれるわけではないので滅失のおそれがあることなどのデメリットがあります。
エンディングノートは正式な遺言として認められる?
遺言と似たようなものとして、「エンディングノート」が挙げられます。エンディングノートとは、自分の判断能力が低下した場合や死亡した場合に備えて、自分の希望を予めまとめておくノートです。
介護の方法や延命治療の希望の有無、葬儀の方法などを記載するのが一般的ですが、自分の財産について記載することも少なくありません。
では、自分の死後に自分の財産をどうしてほしいかエンディングノートに記載した場合、正式な遺言として認められるでしょうか。
ここでは、エンディングノートの基本的な知識や遺言としての効力を持つかどうかについて、詳しく解説します。
エンディングノートは自筆証書遺言にはならない
結論からお伝えすると、エンディングノートは正式な遺言にならない可能性が高いです。 なぜなら、エンディングノートを書く方の大半が、市販のエンディングノートを購入したり、インターネットで公開されているテンプレートをダウンロードしたりして使用しており、正式な遺言としての方式を満たしていないからです。 市販のエンディングノートでは、書くべき項目が整理されているので、誰でも手軽に書くことができますし、重要な項目を書き漏らすことを防げるメリットがあります。ただし、必ずしも正式な遺言としての方式に沿っているとは限らないので、遺言の代わりにエンディングノートを作成するのはリスクがあるでしょう。
エンディングノートは公正証書遺言にもならない
エンディングノートの作成に公証人が関与することはありませんので、公正証書遺言にはなりません。秘密証書遺言として認められる可能性があるが危険である
秘密証書遺言は、署名以外は自書でなくてもかまわないので、エンディングノートに記載したものであっても署名押印や公証人への申述などの条件を満たせば、秘密証書遺言と認められる余地はあります。 ただし、秘密証書遺言のデメリットでも触れましたが、内容に専門家が関与していないため、遺言の内容が不明確な場合やであるとか、法律に違反している場合などはなどの理由で遺言としての効力が認められないリスク危険があります。これらを踏まえると、エンディングノートは正式な遺言として認められないものと考え、別途遺言書作成すべきといえます。
ビデオ遺言は正式な遺言として認められる?
最近では、スマートフォンで誰でも気軽にビデオを撮れるようになったため、家族に対するメッセージをビデオで残す方が増えてきました。
では、ビデオで記録した遺言は正式な遺言として認められるのでしょうか。以下で詳しく解説します。
ビデオメッセージは自筆証書遺言にはならない
ビデオメッセージは、原則として正式な遺言としては認められません。自筆証書遺言と認められるには、証書であること、つまり文書であることが必要です。
ビデオは文書とはいえないので、ビデオ遺言は自筆証書遺言にはなりません。
ビデオメッセージは公正証書遺言にもならない
ビデオメッセージは、公証人が作成する公正証書ではないので、公正証書遺言にはなりません。秘密諸所遺言にもならない
ビデオメッセージは、秘密証書遺言としても認められません。秘密証書遺言にも証書に署名押印することなど、文書を作成することを前提とする方式が定められています。
さいごに|正式な遺言を作成するなら弁護士へ相談を
エンディングノートやビデオメッセージには、手軽なほか、遺言をした人の思いが直接伝わりやすいといったメリットもあります。 しかし、法律上の遺言としての効力は認められません。 正式な遺言を遺したい方は、事前に専門家に相談し、民法に規定された方法を確認したうえで、遺言書を作成するようにしてください。


- 遺言書が無効にならないか不安がある
- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2024.09.17相続手続き代行相続したときに必要な戸籍謄本の取り方・見方・提出先について解説!
- 2024.08.29遺産分割協議葬儀費用や香典返しはだれが払う?遺産分割の対象にできる?
- 2024.08.28遺産分割協議遺産分割の弁護士費用はどれくらいかかるの?費用を抑える方法は?
- 2024.08.28相続税申告・対策弔慰金は相続税ではどのように評価するか解説